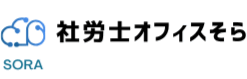ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。
今回は、小規模企業共済についてご案内いたします。
小規模企業共済はこんな制度
小規模企業共済とは、経営者や役員の方のための積立による退職金制度のことです。
個人事業の事業主とその共同経営者の方、また、小規模企業を経営している会社等の役員の方が加入できます。
運営元は独立行政法人 中小企業基盤整備機構です。
小規模企業共済の掛金は、全額を「小規模企業共済等掛金控除所得控除」として、課税対象となる所得から全額控除することができます。なお、事業上の損金や必要経費には算入できません。
受取りの折にも、一括受取りの場合は「退職所得」、分割受取りの場合は「公的年金等に係る雑所得」として所得金額が計算されるため、積立時・受取時の両方で税額を軽減できるとされています。
また、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することも可能です。
加入資格と掛金は?
加入資格
小規模企業共済の加入資格は以下のとおりです。
1.建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業のみ)等を営む場合、正規雇用の従業員数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業以外)を営む場合、正規雇用の従業員数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、正規雇用の従業員数が20人以下の協業組合の役員
4.正規雇用の従業員数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.正規雇用の従業員数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
掛金
掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲内(500円刻み)で指定できます。増額、減額も可能です。(減額には一定の要件があります。)
掛金は、基本的に屋号表記のない、個人名義の口座から引き落としが行われます。
請求事由と要件
共済契約者の事業上の地位や共済事由によって、共済金の金額は異なります。
共済金の請求事由には次の4つがあります。
- 共済金A→廃業、廃業に伴う共同経営者の退任、会社の解散等
- 共済金B→65歳以上で掛金納付の要件(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだこと等)を満たしたことによる老齢給付、疾病・負傷により役員を退任した場合、65歳以上で役員を退任した場合等
- 準共済金→法人成りによる加入資格喪失・共同経営者の退任、65歳未満の役員退任等
- 解約手当金→任意解約、滞納による機構解約
なお、共済金A・Bは掛金納付月数が6か月以上、準共済金・解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支給されます。
加入申し込みについて
申し込みは、申込書を請求の上、確定申告書の控えや履歴事項全部証明書等(加入者の属性によって異なります。)を添付して行います。
申込先は該当窓口の金融機関や商工会議所等の委託団体です。
なお、共同経営者以外はオンラインでも申込が可能です。
まとめ
小規模企業共済のポイント
- 小規模企業共済は、経営者や役員の方のための退職金積立制度
- 掛金は、全額を課税対象となる所得から控除できる。受取時にも税額の軽減がある。
- 掛金は1,000円~70,000円の間で指定できる。増額・減額(要件あり)も可。
- 共済契約者の事業上の地位や共済事由によって、共済金の金額は異なる。
本日のご案内は以上です。他記事も是非ご覧ください。
出典:共済サポートナビ(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)