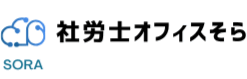ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。
今回は、育児・介護休業法の改正のポイントと、必要な対応についてご案内いたします。
2025年4月の改正
最初に、2025年4月の改正を振り返ります。
①子の看護休暇の見直し(義務)
- 対象となる子どもの年齢範囲が「小学校就学前」から「小学校3年生修了まで」に拡大
- 取得理由の拡大(入園(入学式)式・卒園式、学級閉鎖等を含む。)
- 労使協定により除外できる対象が、週の所定労働日数が2日以下の従業員のみに緩和
- 名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更
②所定外労働の制限の対象拡大(義務)
- 3歳未満の子を養育する従業員が対象だった「所定外労働の制限(残業免除)」などの措置が、「小学校就学前の子」まで拡大
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 短時間勤務制度の導入が困難な働き方の従業員に対して、労使協定を締結した上で代替措置を講ずることが必要
④育児のためのテレワーク導入(努力義務)
- 3歳未満の子を養育する従業員が、テレワークを選択できるようにすること
⑤介護休業を取得できる従業員の要件緩和
- 労使協定により除外できる対象が、週の所定労働日数が2日以下の従業員のみに緩和
⑥介護離職防止のための雇用環境整備・個別周知・意向確認等(義務)
⑦介護のためのテレワーク導入(努力義務)
- 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにすること
2025年10月の改正
①柔軟な働き方を実現するための措置の実施(義務)
3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対して、次の5つの措置のうち2つ以上を選択して導入
- 時差出勤(始業時刻等の変更)
- テレワーク(月に10日以上)※時間単位の取得を原則可能とする。
- 保育施設の設置運営、ベビーシッター手配&費用負担
- 養育両立支援休暇の付与(年に10日以上) ※時間単位の取得を原則可能とする。
- 短時間勤務制度
②柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認(義務)
子どもが3歳になる1か月前までに、柔軟な働き方を実現するための措置の周知と制度を利用するかを個別に確認
- ①で選択した対象措置の周知、申出先
- 所定外労働、時間外労働、深夜労働の制限に関する制度の周知
③仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)
従業員が本人or配偶者の妊娠・出産等を申し出たときと、子どもが3歳になる1か月前までに、少なくとも2回、従業員の意向を個別に確認
- 勤務時間(始業・終業時刻)
- 勤務地
- 両立支援制度等の利用期間
- 業務量、労働条件の見直し
出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室))
会社で必要な対応は?
就業規則を作成している会社は、10月の改正に向けて、「柔軟な働き方を実施するための措置」を選択し、制度として整備しましょう。
措置については、従業員の同意が必ずしも求められるものではありませんが、従業員の過半数を代表する者の意見を聞き、十分なコミュニケーションをとることが望まれます。
制度を整備するだけではなく、社内への周知や従業員の意向確認、管理職の理解、制度を利用しやすい環境作りも併せて進めることが大切です。
こうした取り組みは、人材の定着や育成にもつながります。積極的に制度を整えていきましょう。
本日のご案内は以上です。他記事も是非ご覧ください。