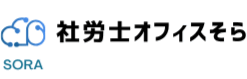ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。
本日は、休日と休暇の違いや、様々な休暇についてご案内いたします。
労基法の休日と休暇の違い
労働基準法の「休日」とは、労働契約において、労働義務がないとされている日のことです。
休日は、原則として午前0時から午後12時までの継続した24時間の休みのことをいいます。
使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
次に「休暇」とは、本来は労働の義務がある日について、労働を免除された日のことです。
休暇には、法律で定められた休暇・休業(法定休暇)と、福利厚生の一環として、事業主が任意に定めることができる休暇(法定外休暇)があります。
※法定休暇の例→年次有給休暇、生理休暇、看護休暇、子の看護休暇等
年間休日数が多いほど、月平均所定労働時間が減るため、割増賃金の単価は高くなります。1時間当たりの賃金を月給÷月平均所定労働時間で計算して、割増賃金の基礎となる賃金を求めるためです。
なお、個々の従業員ごとに付与される休暇については、年間休日数に含みません。
ただし、就業規則等で公休日(会社の定める休日)としていれば、年末年始休暇や夏季休暇、という名称でも休日として扱います。
年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、一定期間勤続した従業員に対して付与される休暇のことです。
「有給」で休むことができる休暇ですので、取得しても賃金の減額はありません。就業規則等の定めにより、通常の賃金、3か月間の平均賃金、標準報酬日額相当額(※労使協定が必要)のいずれかを支給します。
従業員に年次有給休暇が付与される要件は2つあります。
①雇い入れの日から6か月経過していること
②その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。
この要件を満たした従業員には、10日間の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年経過ごとに、新しい年次有給休暇が追加で付与されます。
出典:年次有給休暇とはどのような制度ですか。(厚生労働省)
こちらもどうぞ:年次有給休暇に関する記事はこちら
特別休暇とは
特別休暇とは、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇のことです。
休暇中の給与は有給でも無給でも構いません。
有給の特別休暇を設けたり、従業員の色々な活動を支援するための休暇を設けることは、働きやすい職場作りの手助けになります。
参照:働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)
おわりに
働く方の事情に応じて様々な休み方を選択できるようにすることは、人材確保にも効果的です。
事業主の方は有給休暇の取得を促進した上で、従業員・求職者にとってより良い職場となるよう、特別休暇の導入を検討しましょう。
本日のご案内は以上です。
ご不明点のある事業主の方、労務ご担当者の方はお気軽にお問合せください。