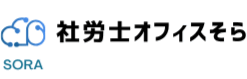ご覧いただきありがとうございます。社労士オフィスそらです。
本日は、高年齢者雇用安定法に定められている、高年齢者の雇用措置についてご案内いたします。
高年齢者の雇用ルールについて
高年齢者の雇用に関するルールは、高年齢者雇用安定法によって定められています。
この法律に定められている「高年齢者」とは、55歳以上の方を指します。
法律の目的は、働く意欲がある高年齢者が、能力を発揮できる環境を整備することです。
具体的には、定年の年齢や継続雇用制度についてのルール、70歳までの就業確保措置の努力義務などが規定されています。
60歳~65歳の場合
従業員の定年を定める場合は、定年年齢は60歳以上とする必要があります。
また、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの雇用確保措置を実施しなければなりません。
上記の措置の中で、一番多く導入されている雇用確保措置が、継続雇用制度の導入です。
継続雇用制度には、定年で一旦退職として、新しく雇用契約を結ぶ「再雇用制度」や、定年で退職とせずに引き続き雇用する「勤務延長制度」等があります。なお、対象は希望する労働者全員です。
勤務延長制度では、基本的に従前と同じ労働条件で雇用契約が継続しますが、再雇用制度では、定年前と異なる労働条件であっても差し支えないとされています。
但し、職務内容が定年前と変わっていないにもかかわらず、給与を大きく引き下げることは、不合理な相違として、違法・無効とされる可能性があります。
また、再雇用契約後に、これまでの労働者の経験や能力とかけ離れた業務に従事させることが、問題視される場合があります。
(※定年前→事務職、再雇用後→清掃業への従事の要請が、違法とされた判例が存在します。)
高年齢者雇用安定法は、高年齢者が能力を活かして活躍できる環境を整えることを目的としています。
その趣旨に明らかに反する処遇は望ましくありません。
65歳~70歳の場合
65歳までの雇用確保義務に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずる努力義務が規定されています。
内容は次のとおりです。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度の導入
- 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に事業主等が実施する社会貢献事業に従事できる制度の導入
上記は、事業主としての努力義務を定めているものであり、70歳までの定年年齢の引き上げを義務付けているものではありません。
まとめ
高年齢者の雇用ルールのまとめ
- 高年齢者の雇用ルールは、高年齢者雇用安定法に規定されている。法律の目的は、働く意欲がある高年齢者が活躍できる環境を整備すること。
- 従業員の定年を定める場合は、定年年齢は60歳以上とする必要がある。定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの雇用確保措置を実施する。
- 事業主には、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずる努力義務がある。
本日のご案内は以上です。
知識や経験が豊富な高年齢者の方が、長期にわたって力を発揮できる環境を整えていきましょう。
ご不明点のある事業主の方はお気軽にお尋ねください。
【ご参考】こちらもどうぞ:高年齢求職者給付金とは
参照:高年齢者の雇用、高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)、高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~、令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します(厚生労働省)